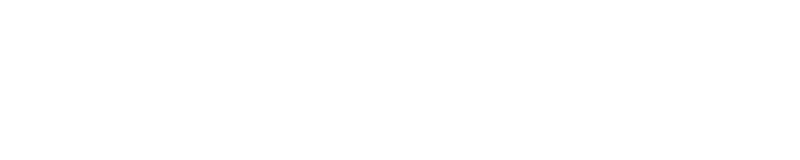どこかしらで必ず見かける道路工事。
道路の利用者側からすれば迷惑な道路工事ですが、大事な作業ですよね。
地下の水道管やらガス管やらの工事のためだったり、道路自体の劣化で定期的に新しくする必要もあるでしょうし。
そこで、ふと今回の疑問が浮かびました。
あんな頻繁に工事で道路を壊しまくっていたら、使用済みの廃棄アスファルトがたくさん出ますよね?
あの壊した後の使用済みアスファルトは、一体どうしているのでしょうか?
どこかへ捨てるのだろうか?
それとも砕いたり溶かしたりして、再利用しているのでしょうか?
というか、アスファルトってそもそも何?
そんなアスファルト道路の疑問について調べましたので、シェアしたいと思います。
道路工事で壊したアスファルトはリサイクルされているのか?

工事で壊した使用済みアスファルトは、再利用されているのでしょうか?
それとも、どこかに廃棄処分されているのでしょうか?
この疑問を解決します。
結論からいうと、
ほぼ完璧に、リサイクルされていました。
驚くべきは、そのリサイクル率。
なんと98%以上が、新たな道路として再利用されているのです。
使用済みアスファルトは、見事なまでにリサイクルが可能なのです。
使用済みアスファルトは、アスファルト混合所という場所に集められます。
そこで破砕機を使用して細かく粉砕し、再生アスファルト(※1)骨材として再利用されます。
劣化で固くなった古いアスファルトは、再生添加剤というもので柔らかくされ新しい骨材と混ぜらてます。
劣化の激しく固くなりすぎているものは、再生(※2)路盤材として使用します。
※1骨材とは コンクリートやアスファルトの調合に必要な砂利や砂のこと。
※2路盤材とは 道路の下地になる部分のこと。
ちなみに道路はケーキみたいな層で作らていて、上から
- 表層
- 基層
- 上層路盤
- 下層路盤
となっています。
4層で道路が完成。
ひとつ疑問が解決して、スッキリ。
そもそもアスファルトとは、いったい何なの?

アスファルトそのものについても、調べてみました。
アスファルトは、日本語で土瀝青(どれきせい)といいます。
一言にアスファルトといっても、2種類が存在します。
- 原油を蒸留して製造する石油アスファルト
- 天然に存在する天然アスファルト
人工アスファルトと、天然アスファルトです。
トリニダード・トバゴには、純度の高いアスファルトが吹き出す湖があるとのこと。
想像できませんよね。
道路工事に使用されているアスファルトは、石油アスファルト。
つまり、原材料は石油。
石油は蒸留すると、LPガス、ガソリン、灯油、軽油がまず分留されます。
そして蒸留して残った重い部分を低圧蒸留して、さらに重油、潤滑油、アスファルトに分留します。
ここでアスファルトが誕生します。
アスファルトとは、黒くドロドロした重い液体なのです。
ですが道路に使用されてるあのアスファルトは、液体ではありませんよね。
道路を指すアスファルトとは、
混合物とアスファルトを混ぜたアスファルト合材(アスファルト混合物)のことです。
それを省略して「アスファルト」と呼んでいるのです。
アスファルト合材とは
アスファルト合材とは石を砕いた骨材と(※3)フィラーに、アスファルトを混ぜた合材です。
※3フィラーとは フィラーとは石灰岩の微粉末。
骨材とフィラーをバランス良く混ぜ、アスファルトで接着しているイメージです。
ちなみに使用される道路によって、骨材のバランスを変えています。
積雪の多い地域の道路はチェーンで道路が削られてしまうため、耐摩耗用にフェラーの割合が多くなっています。
骨材の種類は、粗骨材(大きめの石)と細骨材(小さめの石)があり。
まとめ、結論
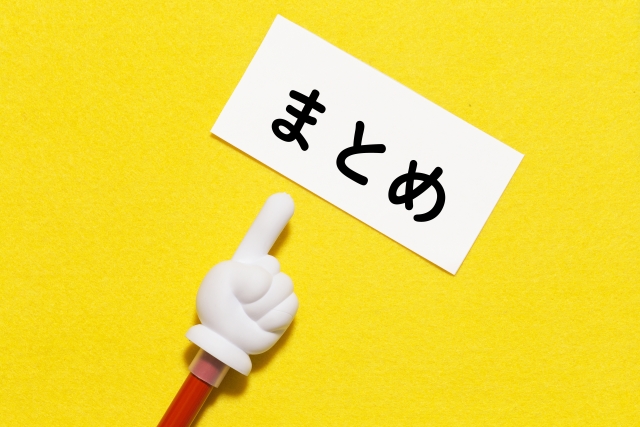
道路工事で壊したアスファルトは、完璧なリサイクル循環が確立されていました。
廃棄処分なんて、ほぼ無かったのです。
完璧で無駄なく、リサイクルされていることには驚かされました。
確かにこれだけ道路工事していてアスファルトを廃棄していたら、日本中が廃アスファルトの山だらけになってしまいます。
98%のリサイクルとは、実に素晴らしい。
それにしても、今回改めて石油の重要性を感じました。
アスファルト道路も、石油が無いと作れないのですから。
資源のことを考えれば他の製造方法で道路をつくることを考えるべきと思いますが、当面はアスファルト道路のままでしょうね。
電気自動車になろうと、石油依存の世の中は続きそうです。
以上、道路工事で壊したアスファルトはどうしているのか?の解決記事でした。