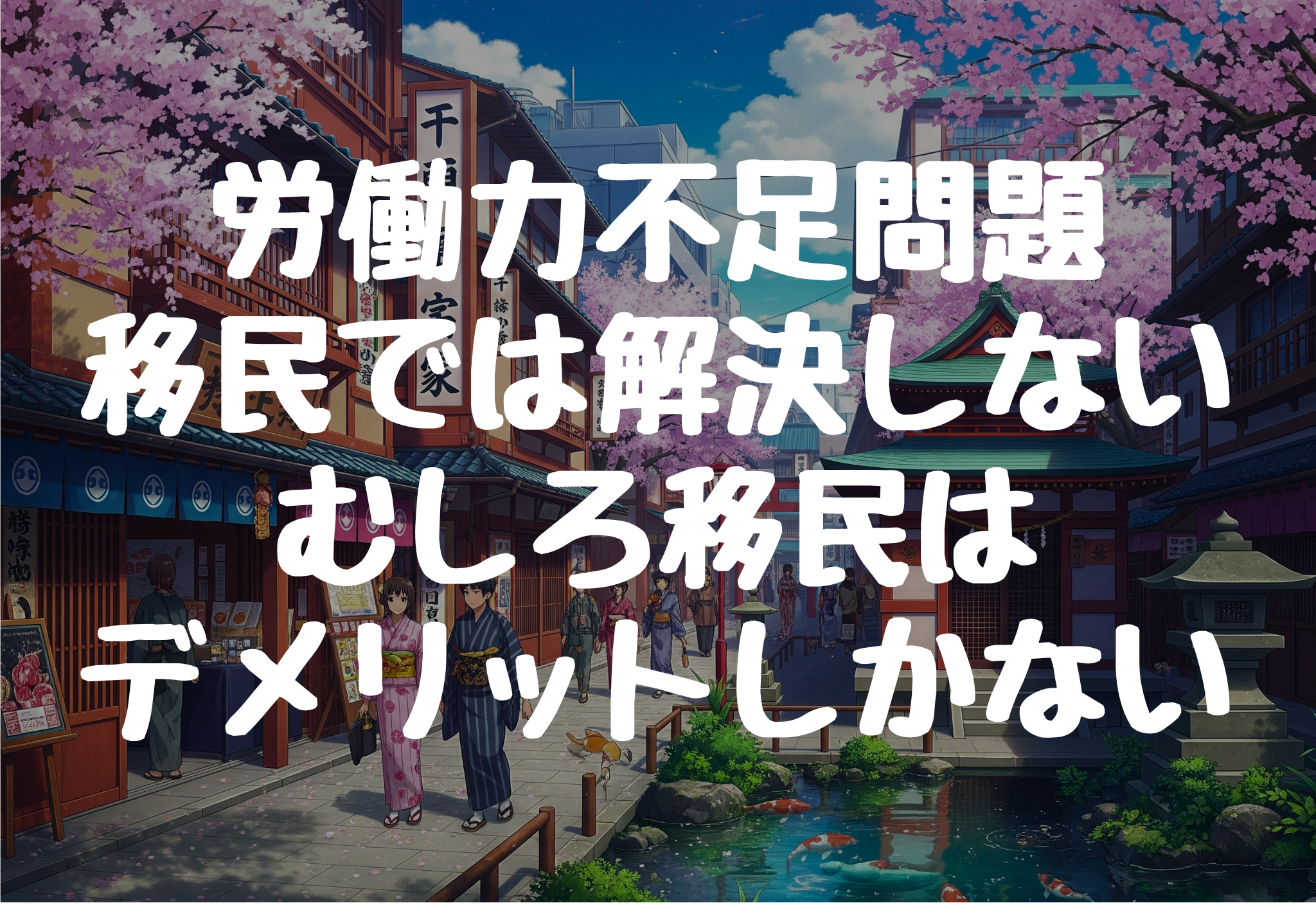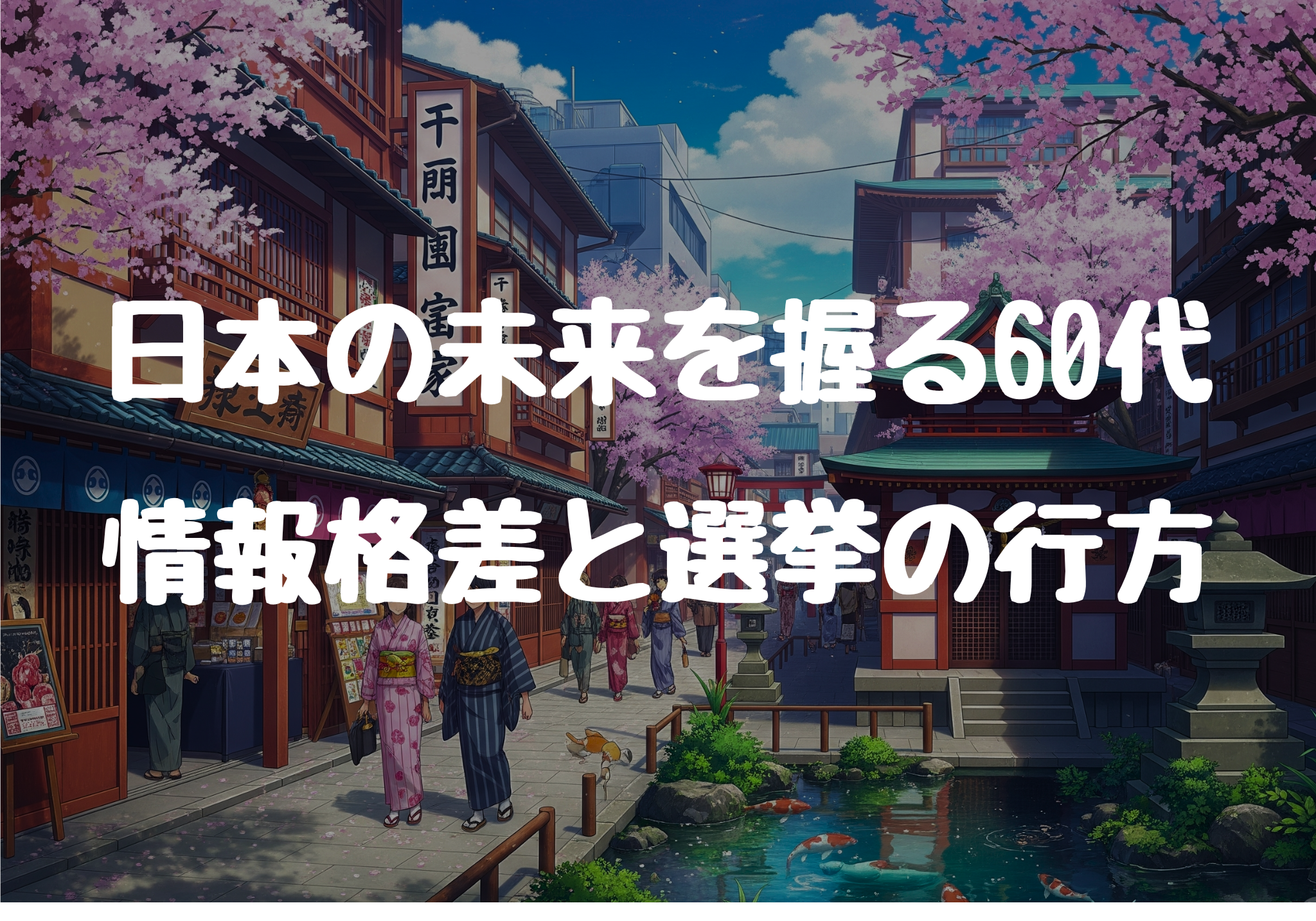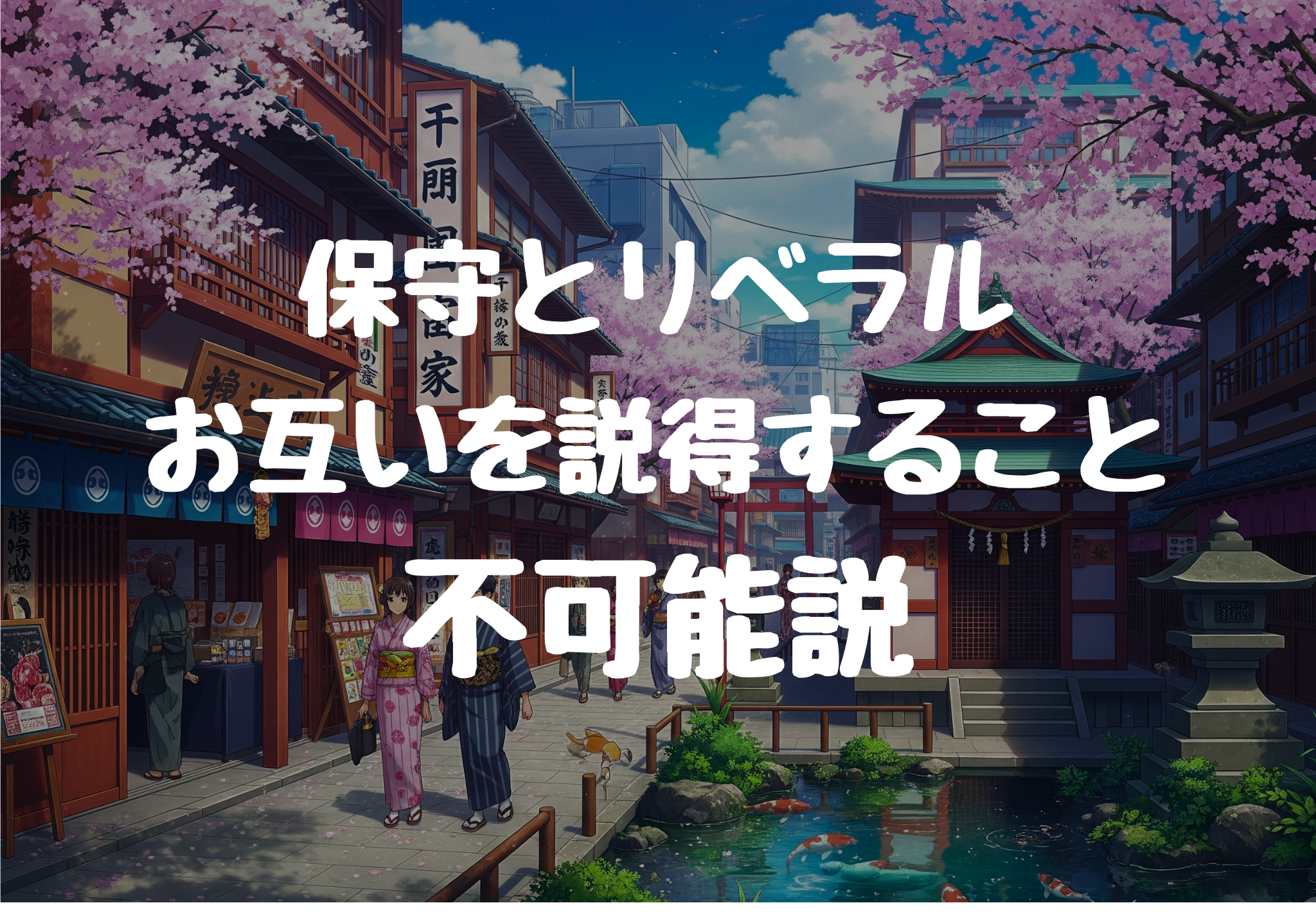男女平等という名の不平等:女性が不利になる現実と、補完し合う理想の形
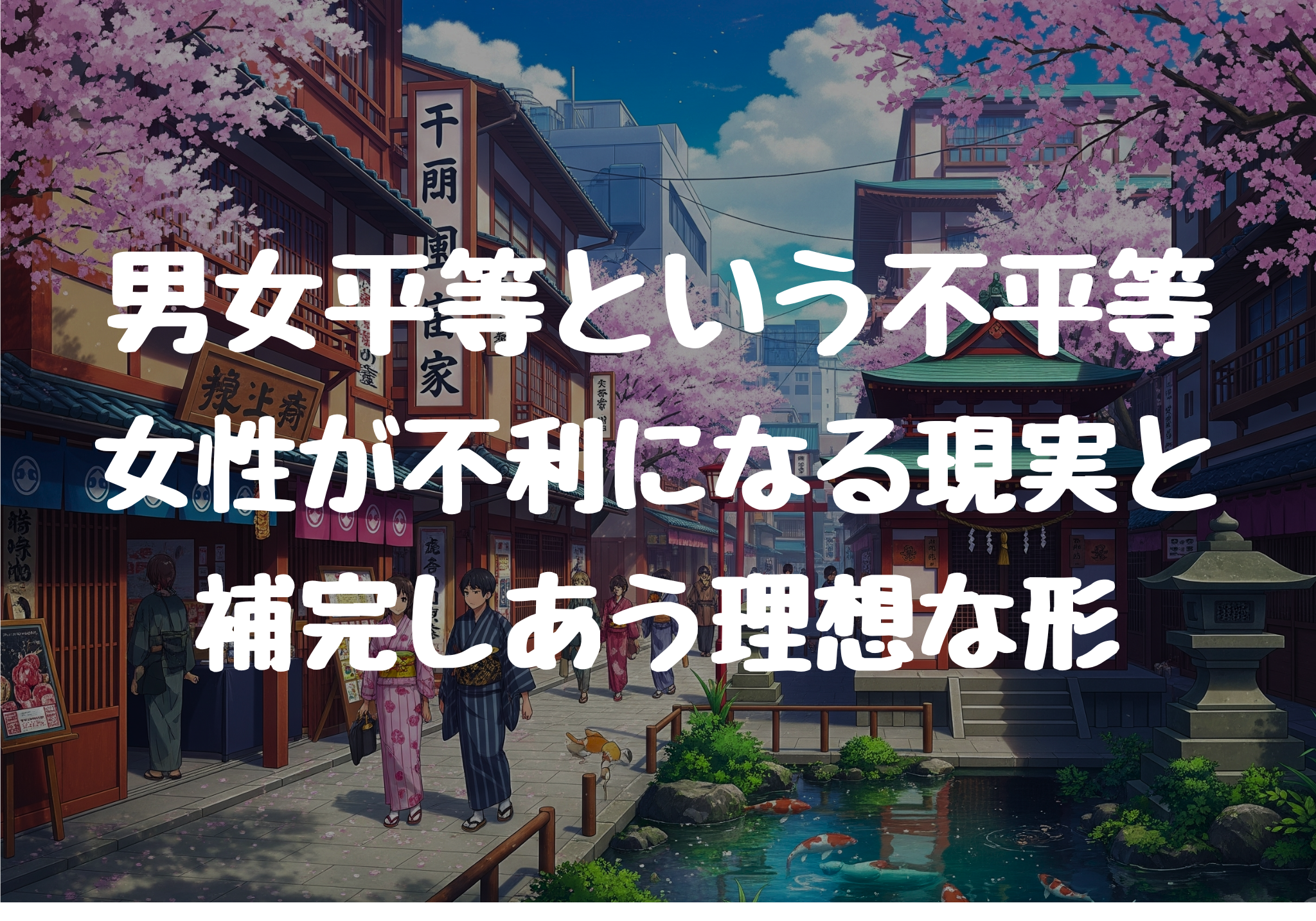
フェミニストが主張する男女平等。
その意図は理解できます。
人類皆平等という考え方は、理想的な社会のあり方かもしれません。
しかしながら、私はこう考えるのです。
男女平等を推し進めるほど、女性にとって不利益な結果を招くのではないかと。
男性には男性の役割、そして女性には女性の役割が存在します。
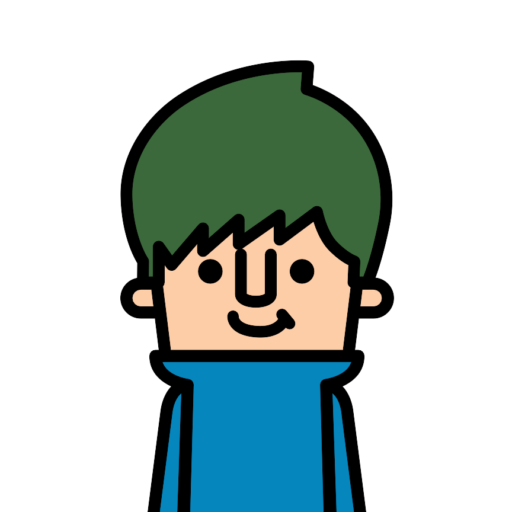
それらを画一的に扱うことが、真の平等と言えるのでしょうか。
今回は、男女平等が女性にとってマイナスとなりうるという考え方を紹介したいと思います。
進む男女平等、見過ごされる女性の不利

一部の女性フェミニストが積極的に推進する男女平等。
その意図は理解できますが、結果として自らの首を絞めることになるのではないかと私は考えます。
なぜなら、身体的な構造の違いから、男女の完全な平等には限界があるからです。
生存戦略としての効率的な役割分担
はるか昔から、男性と女性の役割は明確に分かれていました。
男性は狩猟によって食料を確保し、女性は家庭内で料理や子育てに専念する。
この役割分担は、男性の持つ腕力や体力、そして女性が子供を産み育てるという生物学的な特性に基づいています。
子孫を確実に残すための生存戦略として、この分担が最も効率的であったことは想像に難くありません。
進む男女平等に潜む落とし穴
時代は変わり、現代では男性が狩りをすることはなくなり、お金を稼ぐことが仕事の中心になりました。
力仕事の重要性が薄れ、体力で劣る女性も社会で活躍できるようになったのです。
男女が同じように働き、一緒に子育てをするという形も増えました。
ですが、この男女平等には大きな落とし穴がたくさんあります。
男女が同じことをしようとすると、どうしても女性の方が不利になることが多いのです。
男女平等、その理想と現実の乖離:女性に偏る負担

男女平等の推進が、かえって女性にとって不利な状況を生み出すと考えられる理由を説明します。
体力、腕力の差
体力の差
男女が平等に仕事をする現代の仕組みにおいて、見過ごせないのが体力差の問題です。
たとえ仕事の能力が同等であっても、体力という要素が影響を及ぼすことがあります。
男性の方が一般的に体力や持久力に優れているという、生物学的な差異は厳然として存在します。
体力仕事においては明白ですが、体調の変動が少ない男性は、デスクワークにおいても潜在的なアドバンテージを持っていると言えるのではないでしょうか。
腕力の差
男女間における顕著な差異の一つが腕力です。
一般的に、女性は男性と比較して筋力が約30%少ないとされています。
昭和に生まれた私は、父から「女性や子供には決して手を上げるな」と教えられて育ちました。
当時の価値観として、男女の体力差は歴然としたものであり、男性が犠牲を払ってでも女性を守ることが美徳とされていました。
しかし、現代社会においてはどうでしょうか。
男女平等の考え方が浸透するにつれて、暴力の主体も平等化しているのではないでしょうか。
男女が完全に平等であるという理念が先行し、力による行使も平等であると解釈されるならば、女性が圧倒的に不利なのは誰が見ても明らかです。
体調の違い
女性にとって不利な点は、体力や腕力に限りません。
体調の波もまた、不利な要素となります。
一般的に男性は、病気を患わない限り比較的安定した体調を維持できます。
血液量も常に一定です。
しかし、女性は月経周期により、月に一度体調が著しく変動する時期があります。
体温や血液量も変化し、安定した体調を保つことが困難です。
このような状況下で男女が平等に競い合えば、男性が有利になるのは明らかです。
「女性はか弱い存在であるから、男性がその分を補うべきだ」という昭和の時代に根付いていた考え方は、男女平等の推進に伴い失われつつあるのではないでしょうか。
体調面まで考慮するならば、平等な競争は実質的な不平等を生むと言えます。
出産
男性が担うことのできない、女性固有の役割が出産です。
現代社会は、男女が平等に育児を行うことを目指していますが、イクメンの努力をもってしても、完全な平等には限界があります。
出産による女性の体力低下、そして母乳による育児は、男性が代替できるものではありません。
いかに平等な育児を心がけても、その負担が女性に偏ることは避けられないでしょう。
男女を均すことが本当に平等?現代の限界と補完という考え方

女性が顔を見せるだけで鞭打ち刑に処されるような社会であれば、改善は当然必要でしょう。
しかしながら、日本はそうした状況とは異なります。
過去においては異なっていたかもしれませんが、現代においては女性の権利は十分に保障されていると考えられます。
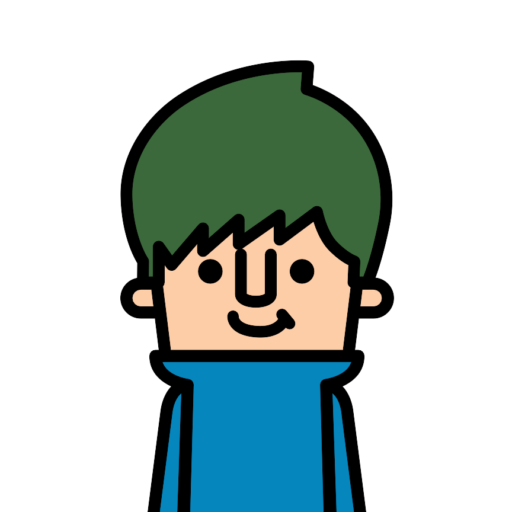
男女を画一的に均すことが、本当に正しいと言えるのでしょうか?
現代の男女平等は限界では?
現代の男女平等は、すでに限界に達しているのではないでしょうか。
このまま男女平等を推し進めることは、むしろ女性にとって不利益を増大させるだけだと考えられます。
結果として、出生率の低下を招き、日本社会全体にとっても好ましい状況とは言えないでしょう。
合理的な役割分担としての男女の補完
私は、男女がそれぞれの役割を果たすことで、不足する部分を互いに補い合う関係が理想だと考えています。
例えば、体力に優位性のある男性が主に経済的な基盤を支え、その不足分を女性が補完する。
また、女性が中心となって育児を行い、手が足りない部分を男性がサポートする。
これは単なる旧来の考え方ではなく、合理的な役割分担であると私は捉えています。
あとがき
男女平等の追求が、皮肉にも女性にとって不利益をもたらすという視点から考察を行いました。
女性フェミニストの方々は、男女平等の理念を実現しようとすることが、自らの首を絞める行為に繋がりかねないという現実に目を向けるべきでしょう。
真の平等とは、それぞれの性別が持つ特性を尊重し、相互の不足を補完し合う関係性を築くことにあるのではないでしょうか。
男性は女性の存在なしには社会生活を円滑に送ることが難しく、同様に女性も男性の支えなしには困難を抱えるでしょう。
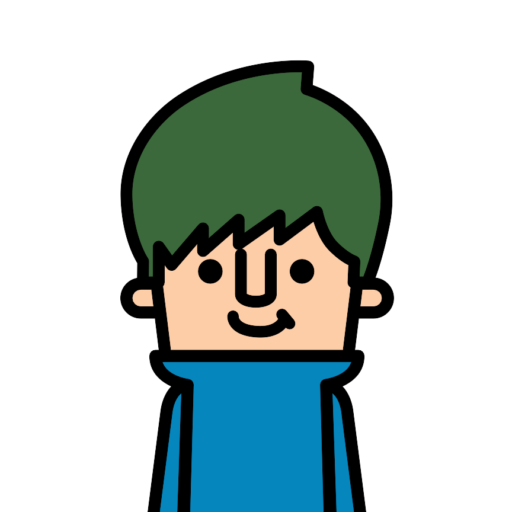
その相互依存の関係こそが、自然なあり方なのではないでしょうか。
お互いを尊重し、協力し、役割を分担することによってこそ、真の男女平等が実現すると考えられます。
男女が同一の職務に就き、同じ基準で競争することは、表面的な平等に過ぎず、実際には女性にとって不利な状況を生み出すだけです。
以上です。
それでは、また。